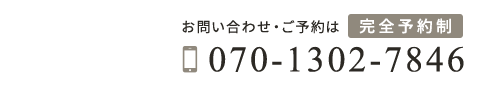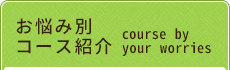【構造と機能の関係性】
ヒトを見る際に大切なことがあります。
それは施術、調整するにあたっての順番です。
例えば、車を思い浮かべてください。
車のタイヤを1つだけ新品にしたとします。
そうすると他の古いタイヤとのバランスがうまくとれず真っ直ぐ走ることが難しい状態になります。
その状態で運転手の技能をあげる訓練とタイヤを変えてあげること、どちらを先にしますか?
年齢を重ねていく度に運動機能は落ちていきます。
元々車の運転が苦手な方もいるかもしれません。
運転技能ばかりにフォーカスしていくよりも、まずはタイヤを変えてあげれば本来持っている運転技能が見えてくると思います。
これは、ヒトのカラダでも言えます。
ヒトのカラダの構造がしっかり整っていない状態で運動療法やトレーニングを頑張ったとしても、効率的なトレーニングにはならないことが多く結果が出にくいです。
理学療法士として病院に勤められている時に良く経験することがありました。
機能訓練を頑張ってやった!!しかし、その患者様が熱発で寝込んでしまい1週間リハビリが出来なかった。
あれ?1週間前まで出来ていたことが出来なくなっている!!
運動機能が極端に落ち、リハビリを最初からやらなくてはいけない!
このような経験をしました。
これは構造自体を丁寧に整え、機能訓練をしていたら結果が変わっていたかもしれません。
治療の順番として、
構造が整っているから機能が上がり、機能が上がるから能力が上がっていきます。
では、構造が整っていない状態で機能だけが上がるとどうなるでしょうか?
構造という土台から機能が優位な状態になります。
機能が優位な状態で構造自体をカバーしようとすると、関節、筋などの固有受容器の発火場所が確保出来ないため、代償動作になります。
リハビリの訓練で機能訓練する時に代償動作のパターンを上手に使えるように設定していく場面もありますが、基本的に代償動作はそのヒトの動ける幅の限界範囲で出てくるものなので、組織の固有受容器の発火は起こらないため、その場所で訓練していても動きの学習にはならないと言う訳です。
構造→機能→能力→社会の順番で介入していくことを行うことで、今までにない効果が発揮されます。